- イベント第1回オープニング・参加案内
- イベント第1回リアクション
- イベント第2回オープニング・参加案内
- イベント第2回リアクション
- イベント第3回オープニング・参加案内
- イベント第3回リアクション
- イベント第4回オープニング・参加案内
- イベント第4回リアクション
- イベント第5回オープニング・参加案内
- イベント第5回リアクション
- イベント第6回オープニング・参加案内
- イベント第6回リアクション
- イベント第7回オープニング・参加案内
- イベント第7回リアクション
- イベント第8回オープニング・参加案内
- イベント第8回リアクション
- 七夕特別シナリオ オープニング・参加案内
- 七夕特別シナリオ リアクション
- 8月度休日シナリオ参加案内
- 8月度休日シナリオ リアクション
- 9月度休日シナリオ参加案内
- 9月度休日シナリオ リアクション
- 10月度休日シナリオ参加案内
- 10月度休日シナリオ リアクション
- 日常シナリオ参加案内
- 日常シナリオ リアクション
- ファイナルシナリオ参加案内
- ファイナルシナリオ リアクション
イベントシナリオ第3回リアクション
『あなたにお花を』
展望台に景色を見に行こう!
リック・ソリアーノたちの呼びかけに応えて、町や館から、多くの人が集まっていた。
お弁当が完成したら、ハイキングに出発だ。
楽しい一日が始まろうとしていた。
第1章 まごころの味、お弁当作り
厨房からは、美味しそうな音と匂いが漏れ出している。
「これはお弁当には、絶対欠かせない一品なんです」
岩神あづまの振るうフライパンの上には、タコさんソーセージが踊る。
「あら、可愛い」
カヤナ・ケイリーはそれを、しげしげと見ていた。
「はい、出来上がり」
粗熱をとるために、皿の上に乗せられた愛らしい姿のソーセージ。カヤナは「これ、今度私も作ってみようかなぁ」とこぼした。
「オススメですよ。子どもからの人気も高いですし」
あづまが笑っていうのに合わせて、彼女が「そうなんですか」と微笑む。
「こっちはなんですか?」
カヤナが指さした先には、銀のボウルと、その中に漬け込まれた鶏肉があった。
「それですか? それは、真砂でも人気の、『鶏のから揚げ』です。これから揚げるところなんですよ」
「へぇ……ニンニクとショウガの、いい香りがしますね」
「ええ。特製の漬けダレで、優しい野菜の甘味が隠し味なんです」
あづまの説明に、「なるほどなぁ」と、カヤナはうなずいた。
「勉強になりますね」
「いえいえ、こちらこそ、カヤナさんから学ばせていただいていますよ」
あづまは、カヤナの作ってきたポテトサラダを見た。
「お相伴にあずかっても、いいですか?」
「どうぞ。その代わり、私もこの胡麻和え、少し味見させてくださいな」
「ええ、どうぞ」とあづまは頷いた。ブロッコリーと人参の胡麻和えは、お弁当向きに、少しだけカットサイズを大きめにしておいたのがポイントである。
カヤナはそれを一口食べて、「んんっ!」とうなった。
「この塩加減に、ほんのりした酸味とゴマの風味……これは、ヤミツキになるっ!」
彼女はそう言って、もう一度フォークを持った手を伸ばそうとしたが、「あ、お弁当か」と言って、ゆっくり引っ込めた。
「カヤナさんのポテトサラダも、すごくおいしいですよ」
あづまは興奮を抑えるように、つぶやく。
「ぴりっと黒コショウが効いていて、シンプルだけど、奥が深い……このレシピ、よければ教えて下さいませんか?」
「ええ、いいですよ」
カヤナはニコっと笑って、ペンと紙を取り出した。
第2章 展望台にて
「うーん……」
ヴォルク・ガムザトハノフは、粗く形の見え始めている像を目の前に、小さくうなった。彼が作ろうとしているのは、自身の名前の由来にもなっている、オオカミである。まだ、その全容は見えないが、ヴォルクには、ここからどうしていくべきか、その道筋がわかっているのかもしれない。
「んん……」
指先に意識を集中し、わずかな木片を削り出す。切り落とされた木屑が、丘の上に飛び散った。そして、少し削っては、またうなる。
「うーん……」
風の刃で像を掘り落としていくというこの工程は、彫像を作るための美的感覚はもちろんのこと、集中力と、高い魔法のコントロール力が要求される。少しでも手元が狂うと……。
「あっ……」
ヴォルクは小さく悲鳴を上げた。
「ふぅ……危なかった……」
わずかに手元が狂ったようだったが、幸い、大きなミスでは無かったようだ。彼は再び、目をキリリとさせ、像を、じぃっとにらんだ。
「できる……できる……オレなら……ヴォルク・ガムザトハノフなら……できる……!」
彼は自分にだけ聞こえるほどの、小さな声量でそう言うと、再び手先に全神経を集中させる。
……そして。
「できたぁっ……! くっ……はっはっはっはっはぁぁっ!! やはり、オレにかかれば、この程度、造作もないわ!」
ヴォルクは彫像を持ち上げ、天高く掲げた。そして、振り返り、遠くから丘を登ってくるはずのあづまを、じっと待った。彼は、あづまに渡すために、これを作っていたらしかった。
アウロラ・メルクリアスは、太めの木の枝を杖代わりに、山をゆっくりと登ってきていた。展望台まで辿り着いた彼女を、新鮮な空気と、柔らかい花の匂いが待っていた。
「んー……っ……!」
一緒に登ってきたトゥーニャ・ムルナが、彼女の横で大きく伸びをする。
「っはぁーっ……気持ち良いーっ……!」
「そうだね……」
脚に不安のあったアウロラは、しかし、しっかりと山を登り切れたという安堵も相まって、実に穏やかな表情を浮かべている。
「わぁ……ここからだと、結界内が一望できるんだー……」
額に浮かんだ汗をぬぐって、彼女はぐるりとあたりを見回した。
「さ、お昼ご飯にしようっ!」
トゥーニャが大きな声で言うと、アウロラも、「うん!」と応じた。
展望台の真ん中で、コタロウ・サンフィールドは、カヤナが持ってきた弁当にフォークを伸ばし、「この弁当、すごく美味いよ。本当にありがとう!」と、感謝しきりである。
「しかし、ピクニックなんて久しぶりだし、すごく新鮮な気分だね」
コタロウのことばを受けて、傍に腰を下ろしたトゥーニャは、「ホントにねー」と笑った。
「最近危ないニュースばかりだし、どうしても暗くなっちゃうからね」
そう言ったアウロラは、わずかに表情を曇らせたが、それでも、この景色の前に、また明るい笑顔を取り戻す。
「温泉の時もそうだったけど、明日から頑張って働く元気が充填される感じがするよ」
コタロウのことばに、うんうん、と、一同がうなずいた。
「あっ、サンドイッチ!」
トゥーニャは、アウロラが広げたお弁当を見て、キャッキャと喜んだ。
「あるもので、って感じなんだけど……」
「おいしそう~っ!」
「……食べる?」
トゥーニャのテンションに、アウロラは思わず微笑んで、サンドイッチを差し出した。
「いいのっ?」
「うん」
「わ~いっ!」
両手を宙に大きく伸ばして、トゥーニャは喜びを表現する。
「じゃあ、ぼくのおにぎりもどうぞ!」
彼女が包みを開けると、中から純白のおにぎりが顔をのぞかせた。
「ちょっと贅沢して、漬物も持ってきちゃったー!」
一足先に昼ご飯を終えたコタロウは、彼女らの傍らで、ごろんと仰向けに寝転がったまま、空を見ている。穏やかな空気と、にぎやかな声。
「二年前にここに来たばかりだからさ、こうしてマテオ・テーペを眺めるのって、初めてなんだ」
アウロラは、うーん、と小さく漏らした。
「そんなに大きくないな、とは思っていたけど、こうして見ると、やっぱり狭いんだね、ここって……」
「そうだね~……」
トゥーニャも同じように、うーん、と続ける。
「だんだん狭くなってるんだよねぇ……大丈夫かなぁ……」
2人はそれから、少しだけ沈黙した。
「まっ」
トゥーニャが、明るい声をあげる。
「深く考えても仕方ないよ~。今は、この気持ちいい景色を眺めながら、美味しくご飯にしよう!」
「……そう、だね……」
アウロラは、少しだけ悩んだようだが、大きくうなずいて、さらに言葉をつづけた。
「うん、そうしよう」
2人の会話を、ただ黙って聞いていたコタロウは、ふぅ、と小さく息を吐いた。この展望台から見える天井、結界の向こう側にあったはずの、彼の様々な思い出の地を回想する。こころの中に、それらの景色が浮かび上がっては、消えていく。
みんな、同じような不安を抱えているのだ。ここだって、コタロウが思い出したような土地たちと同じように、いずれ水没してしまうのではないか、と。その前に、箱船が完成するのか……それとも……。
「ふぅ……」
コタロウは、ぐっと上体を起こして、大きく背伸びをした。トゥーニャの言う通りだ。ただ考えるだけでは、何も始まらない。明日も、造船の仕事がある。今はただ、それに打ち込むのが先決だ。その合間にある、こうしたわずかな休息は、絶対不可欠のものである。
リック・ソリアーノが、カヤナと一緒に、開かれたランチパックの後片付けをしている。そこに、コタロウ、アウロラ、トゥーニャの3人が加わる。
「今日は、ありがとう」
「え?」
突然のコタロウの言葉に、リックは驚いた。
「どうしたの?」
「こういう楽しい企画を開いてくれて、みんな、癒されているからさ。お礼を言おうと思って」
コタロウの笑顔に、リックは、「そう?」と、笑顔で返した。
「カヤナさんも、お弁当、本当にありがとう。とっても美味しかった」
「お礼なら、私だけじゃなくて、あづまさんにも言った方がいいんじゃない? おかげさまで、私も新メニュー思いついちゃったし」
カヤナは肩をすくめて、目をちらりと、展望台の奥へとやった。
一団から少し離れたところで、彫像を手にしたあづまが、ヴォルクの相手をしているのが見えた。弾けんばかりの彼の表情に、「いい笑顔」と言って、思わずトゥーニャは吹き出した。
「ようやく着くか~! さすがに坂道はこたえるなぁ。リュネ、大丈夫か?」
「ええ、なんとか。今こんなことを言うのは何ですけど……帰りの下りも、油断しないよう気をつけねばなりませんね」
「ああ。上り坂より下り坂のほうが危ねぇって言うしな」
展望台への坂を上る集団の後方を、おじさん二人がふぅふぅ言いながら上っていた。
フレン・ソリアーノとリュネ・モルである。
あと一歩、もう一歩と足を動かしているうちに、やっと二人も展望台に到着した。
「おーおー、けっこうな眺めじゃねぇか」
「我らが造船所がある池も見えますな」
広がる景色に上り坂で酷使された体の疲れが癒されていく。
ゆるゆると歩いていた二人はいつしか足を止め、池の端にある造船所を見下ろした。
ここから見える造船所は小さいが、あそこにこの先の未来がかかっているのかと思うと、リュネは気持ちが引き締まるのを感じた。
あの場所で年長者であることには変わりないが、だからといって老け込むことはできない。
まだまだ働かねば、と思った時、横から大きな腹の虫の鳴き声が聞こえてきた。
「おっと失礼。池を見てたら魚のことを考えちまってな」
どうやらリュネが決意を新たにしている時に、この男爵はとても呑気な世界にいたようだ。
そして開いた弁当箱。
ごくふつうのサンドイッチだったフレンに対し、リュネはブロッコリーが占める割合が多かった。中でもブロッコリーとニンジンの胡麻和えはおいしそうだ。
フレンからの視線に気づいたリュネが説明を始める。
「今日のお弁当のお題はブロッコリーでして。これは花だけでなく茎も食べられるんですよ。塩茹でしてベーコン巻いて焼いて良し、細かく刻んでマヨネーズと黒コショウを混ぜて炒めても良し」
「酒がほしくなりそうな一品だな」
そうかもしれませんね、と笑うリュネ。
「俺は料理はさっぱりだ。お前さんは器用だなぁ」
「男やもめが長いだけですよ」
「一緒になってくれそうな女はいなかったのか?」
不思議そうに尋ねるフレンに、リュネは自嘲気味に唇を歪めた。
「どうも私は、何かに夢中になると他のことが極端におろそかになるようでして……呆れられてしまうのです。おかげで結婚まで行きついたことがありません……」
「そういうところは不器用なんだな……」
フレンはリュネに少し同情した。
すると、今度はリュネがフレンの家族のことを聞いてきた。
「リックの上に長女と長男がいるがもう独立しててな、今はどこで何しているやら」
呑気な言いようだが、実際は行方不明だ。大洪水の時に彼らが何をしていたか、フレンは知らない。この地にいないことだけは確かだ。
「後は、家に元気な女房がいるぜ」
自宅はマテオ・テーペ内にあるという。
「そうですか。立ち入った質問、失礼しました」
「たいしたことねぇだろ。さぁて、メシ食ったら昼寝でもするか」
「気持ち良さそうですね」
いつか本物の青空の下で昼寝ができるように。
そんな日が来ることをリュネは願った。
「おい」
「ふにゃあ……?」
腕に衝撃を感じて、メリッサ・ガードナーは目を覚ました。
「……あれ? レイザくん」
「あれじゃない。人を呼びつけておいて、大股開いてよだれ垂らして寝てるとは何事だ」
「え?」
メリッサは体を起こして、慌てて口を拭う。……特に濡れてはいない。
足も開いてなかったと思う。随分とスカートはまくれてたけど。
不思議そうな顔をしていると、くすっとレイザ・インダーが微笑した。
「冗談だ。凄く幸せそうな顔して寝てたぞ。起こして悪かったな」
レイザはメリッサの隣に座った。
「お弁当にとっても美味しいブロッコリーが入ってたから! 景色も綺麗だし」
メリッサは、笑顔で遠くに見えるマテオ・テーペを指し示す。
そして、レイザを待っている間に作っていたものを、ぽいっと彼の頭に乗せた。
「シロツメクサには約束って意味があるのよ。サポートの件、忘れないでね?」
それはシロツメクサで作った花冠。
「四つ葉もやっとみつかったからあげる。幸運のお守り・改!」
手紙を出した時には見つけられなかった四葉のクローバー。随分探してようやく1つだけ見つけ出したのだ。
「要らなかったら誰かにあげてもいいよ。
あー……でも、渡す相手には気をつけて? どっちにも違う意味もあったりするから……」
「意味?」
「うん、約束、幸運」
メリッサは、花冠、クローバーの順で指差して言い、もう1度同じ順番で指をさし、ごにょごにょとこう続けた。
「私を思って。……私のものになって」
最初にレイザに話した意味よりも。本当はこちらの方がメリッサの真意に近いのだけれど。
「アシルさんには渡さないぞ」
「……え?」
突然のレイザの言葉に、メリッサは驚きながら彼を見た。
「お前、俺をオトして、館に入り込み、アシルさんに接近してねんごろになるのが目的なんだよな」
「なんで?」
「なんでって、それが目的で俺に近づいたんじゃなかったか?」
「……あ、ああ。そうじゃなくて、ええっと、そう、マテオ・テーペ。登頂のためだってば。レイザくんが協力してくれるのなら、それでいいの。だから約束、忘れないでね?」
複雑な気持ちになりながら、メリッサはそう言った。
アシルには渡さない……その言葉が、メリッサを他の男には渡さない。そんな風に聞こえて。
なんだか胸の奥がぎゅっとなった。
(解ってるよー。私は選ばれない女だもの)
でもそんな都合の良いことなどありはしない。
「お前が反故にしない限り、忘れないさ」
「それなら大丈夫だね。私も約束守るから」
彼から視線を移し、メリッサは咲く花々を眺めていく。
「ね、お屋敷にはどんな花があるの? 普通なら薔薇が見頃になってきて、手入れに気合いがはいる時期よね……」
「今は、少しの薔薇と、百合……それから、紫陽花を良く見かける。それから、これも咲いている」
レイザは自分の頭を指差すと、懐から取り出した小瓶をメリッサの手の上に置いた。
「これ……四葉のクローバー?」
透明の小瓶の中に入っているのは、葉が4枚のクローバーだった。
「見つからないって言ってたから」
「もらっていいの?」
「要らなかったら誰かにあげてもいいぞ」
「要るよ! 要る要る。ありがとう」
メリッサは両手でぎゅっと小瓶を握りしめて微笑んだ。
幸せを感じる彼女の微笑みを、目を細めて穏やかな顔でレイザは見ていた。
第3章 お花摘み
展望台から少し下った丘陵地に、リエル・オルトの姿があった。彼女は、自身のお弁当の1品と引き換えに教えてもらった、「ムラサキツメクサ」を探している。ムラサキツメクサは、この丘にはそう多くはないが、ミツバチが蜜を集める花としても知られているらしい。
ふと、展望台から、カヤナが下りてくるのが、彼女の視界の端に入った。
「こんにちはーっ」
離れたところから、大きく声を上げ、両手を振った。カヤナはそれに気付いたらしく、手を振り返している。
「この前は、ありがとうございましたーっ! 今日は、楽しんで下さいねーっ!」
「ありがとうーっ!」
カヤナはそう返事をして、遊歩道を外れ、草の広がる野へと入っていった。その後姿を目で追って、またリエルはムラサキツメクサ探しを再開する。
「んっ」
ふと、その次の一歩で、足元に赤紫の花を見つけた。
「なんだ、何か見つけたか?」
彼女に、そう声をかけたのは、ヴァネッサ・バーネットである。
「ええ、アカツメクサを」
「ほう」
リエルの見ている先を、彼女ものぞき込んだ。
「確かに、アカツメクサだな……ここにも、咲いているのか」
彼女は興味深そうに、うむ、と言った。
「ヴァネッサさんは、何か見つけられましたか?」
「あたしはさっき向こうで、エンレイソウが、小さい規模だけど、群生しているところを見つけたぞ」
「エンレイソウ、ですか……!」
驚いて、リエルは目を丸くした。
「ああ、根や茎に毒があるらしいからな、たぶん誰も手を付けなかったおかげだろう」
「なるほど」
案内しようか、というヴァネッサの提案に、彼女は、よろしくお願いします、と答えた。
「わぁ……きれい……!」
リエルは、思わずそれ以上、ことばを紡げなかった。半径1メートルほどの小さな範囲に、3つの白い花びらをしたエンレイソウが、いくつも生えている。
「……手折るのはもったいないですけれど……」
彼女は「うぅん」と言って、花弁をじっと見た。
「……お店のお客さんにも、見てもらいたいですものね……それに……」
リエルは、瞬時、心の中に、両親の顔を思い浮かべた。それから、思い立ったように、1番手前にあったエンレイソウの根を掘り起こす。
「持っていくなら、気を付けて扱えよ。間違って食べたら、毒だからな」
「はい、ありがとうございます」
リエルは、丁寧に、傷をつけないように、エンレイソウを掘り起こしていく。
ヴァネッサが探しているのは、植物の種であった。エンレイソウは、今まさに花が開いたばかりのようで、種は出来ていない。リエルを置いて、彼女はさらに別の場所へと足を向ける。
「んー……」
ヴァネッサは、野に腰を下ろし、あたりを見回した。意外と、種は多くない。花の盛りとなっているわけでもないが、牧草のような低く小さな草が多いように感じる。体力に自信のな
い彼女は、のんびりと休憩しながら、種探しを続けていた。
「こんにちは」
どこからともなく現れた、メイド服姿のステラ・ティフォーネが、ヴァネッサの隣に、腰を下ろす。
「休憩ですか?」
「ああ、まあ、そんなもんだね。あんたは?」
「さっきまで展望台で食事を。これから、花を摘む予定です。館の面々も、おそらくは気が滅入っていることでしょうから、少しでも慰みになればと」
ステラのことばに、ヴァネッサは、そうかね、と言った。
「みんな、元気そうにみえるけどねぇ、医者のあたしに言わせたら」
「気を張っているのですよ、きっと」
ステラは表情を変えず、それでも声色だけで、わずかに笑って見せた。
「あなたも、花を?」
「ああ、いや、あたしは種を探してるんだ」
「種」
ステラが、不思議そうな顔をした。
「なぜです? どうせなら、咲いている花を探したほうが、面白いでしょう?」
「いやいや、咲いた花もきれいだけどさ。新しく行き着いた場所で、根を張って、力強く育っていく草花の姿、っていうのも、いいだろ?」
ヴァネッサは、目を輝かせる。
「人もこうやって、根を張って生きていかなくちゃいけないな、って、そんな気持ちにさせられる。どんなに慣れない場所……例えば、このマテオ・テーペでもさ」
ステラは、首を傾げた。
「あなたは、もうしっかりと、ここに根付いているのでは?」
「どうだろうな」
ヴァネッサは、足元の草を、じっと見た。
「ま、箱船に乗るときは、みんな健康体で送り出してやるよ。それが、あたしがここで咲いている理由だから」
「頼もしいおことばです」
ステラはゆっくりと立ち上がると、それでは、と言った。
「素敵な種、見つかるといいですね」
「ああ」
ステラの背中に、彼女はそう返事をした。
バート・カスタルは、「ふぅ」と、満足そうに腹をさすっている。
「こんなにいっぱい、しっかりと食事をしたのは、しばらくぶりかもしれないぞ」
そう言うと、「お口に合ったなら、よかったんですけれど」とピア・グレイアムが笑った。
「おいしかったよ、特に、肉の入ったサンドイッチ……あれは絶品だな。サニーでも売っているのか?」
彼の言っている『サニー』とは、ピアの経営している『ベーカリー・サニー』のことである。
「それは、来てみてのお楽しみです」
ピアが笑うと、バートもつられて笑う。
「それにしても、本当に、今日は来て下さって、ありがとうございます。バートさんの休日の、ちょっとした息抜きになれば、と思ったんですけれど」
「いやいや、こちらこそ、誘ってくれてありがとう。こうしていると、本当に穏やかな気持ちになれて、良い感じだ」
いつものキリリとした感じとはどっか違う、素顔のバートが、そこには座っているようだった。
「これ、どうぞ」
ピアは、小さく数輪の花がまとまったものを、バートの胸ポケットに、ちょこん、と挿した。
「ん……これは……?」
「作ってみました。どうです?」
「可愛らしいな」
彼はそれをつまみあげ、そして、匂いを嗅いだ。
「それに、甘くて、いい匂いだ……」
「そうですか? よかった」
「パン屋だけじゃなくて、花屋も開くつもりなのか?」
「えっ?」
突然のバートのことばに、ピアは驚いて目を見開いた。
「お花屋さん、ですか?」
「冗談冗談」
バートの口から冗談が出るとは思っていなかっただけに、彼女は面食らって、そして笑いを我慢できなくなった。
「あははは……面白い……!」
ひとしきり彼女は笑って、それから「サニーの店内にも、飾ろうと思っていたんですよ」と付け加えた。
「今日ピクニックに来ることが出来なかった人も、こういう風に花を見れば、きっと元気が出るんじゃないかな、って」
「いいアイディアだ」
バートは感心したように、うんうん、とうなずいて見せた。
「私、これからお店の為に、お花を摘みます。良ければ、バートさんもご一緒にいかがですか?」
「ん、俺は花のことなんて、まったくわからないぞ?」
「いいんです。こういうのは気持ちが大事なんですから」
ピアのことばに、「それなら」とバートも応じた。
「よろしくお願いしますね」
「こちらこそ」
「……あ」
花を摘もうと、一歩足を踏み出したピアが、振り返ってバートを見た。
「もし、四葉のクローバーを見つけたら、押し花の栞にして、今度お渡ししますね」
リック・ソリアーノと山道を並んで歩いてきたイリス・リーネルトは、景色を堪能した後、四葉のクローバーを探していた。
「なかなか見つからないねぇ。ねぇ、イリス。四葉が見つかったら、お父さんにあげるの?」
「ん……内緒」
「え、内緒なの? う~ん、ますます気になっちゃうなぁ」
軽く口を尖らせて、手元のクローバーをかき分けているリックの姿に、小さく笑みを浮かべるイリス。
正直に答えた時の顔も見てみたいけれど……それはまた、別の機会で。
少しの沈黙の後、今度はイリスがリックに聞いた。
「リックは、女性に花を贈るとしたら、どんなふうに贈る?」
唐突だったのか、リックはきょとんとした顔をした。
「ちょっとした興味本位だよ」
「ん~……そうだなぁ、僕なら……その人の好きな花を贈りたいな」
「好きな花がわからなかったら?」
「好きな色の花とか」
「もし、それもわからなかったら?」
「その時は、僕の好きな花をあげる。それで、その人も僕があげた花を好きになってくれたら、とても嬉しいよ」
「そっか。うん、答えてくれてありがとう。ねぇ、向こうのほうも探してみない? この辺、ないみたいだし」
「そうだね」
二人は場所を変えて探し始めた。
四葉のクローバー探しは人を無口にさせるが、この二人もいつしか手元にのみ集中するようになっていた。
そしてどれくらい経っただろうか。
「見つけた!」
と、声をあげたのはイリスだった。
「ほんと!? 見せて見せてっ」
声を聞きつけたリックが駆け寄って来て、イリスの手元を覗き込んだ。
そこには、ほぼ均等な大きさの葉を四枚つけたクローバーがあった。
「やったね、イリス!」
「うん。これをね……はい、リックにあげる。リックに、幸せがたくさん来るように。……ね?」
差し出された四葉をリックは呆然と見つめた後、ほんのり頬を赤くして、
「ありがとう。大事にするね」
と、照れくさそうに受け取った。
つられるようにイリスも口元を緩めた時、今度はイリスの前に小さなブーケが差し出された。
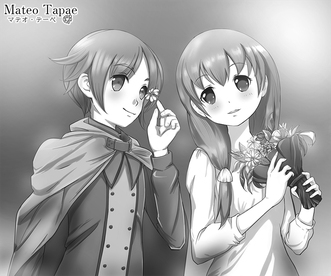
「いろんな花があって、すごくきれいだったから。今日の思い出にと思って」
「……いいの?」
頷くリックから受け取った小さなブーケには、黄色やピンク、橙、白などが集まっていた。
イリスは先ほどのリックとの会話を思い出す。
リックは、イリスが好きな花や色を知らないはずだ。
それなら、このブーケはここにある花でリックが気に入ったものを集めた花ということになる。
イリスの胸があたたかくなった。
「ありがとうリック。わたしも、大切にするね」
お互いの贈り物を手に、二人は幸せそうに微笑み合った。
第4章 色とりどりの思い出を
リルダ・サラインのもとに、トモシ・ファーロがやってきたのは、夕方のことだった。
「お疲れ様」
彼はそう言って、リルダに、一葉の栞を手渡した。
「え、これは?」
「押し花の栞。今日、ピクニックだったから」
「ああ、そっか……忙しくて、すっかり忘れてた……ありがとう」
リルダは穏やかにほほ笑むと、「立ち話もなんだし、上がっていく?」と家の奥を見た。
「いや、お邪魔するのも悪いし、ここで」
「ああ、そう?」
リルダは、それならいいんだけど、と言った。
「どうだった、ピクニックのほうは」
「景色が、すっごく綺麗だったよ」
トモシは、興奮したようにそう告げる。
「いつも地上から見ている港町や造船所も、ああやって高い所から見ると、全然違って見えるんだよね……人が、アリくらいの大きさに見えてね」
「うんうん」
「それに、花や小さな木なんかもあって、本当に綺麗だった……リルダさんも、行けたら良かったのに」
「んー……仕事がね、なかなか……」
彼女は、わずかばかり、苦しそうな表情をした。
「……たまには、ちゃんと息抜きもしてね? 働きづめじゃあ、大変でしょ?」
「そうだけどさ」
リルダは、おどけて言った。
「ここに住むみんなのことを考えたら、なかなか、手も休まらなくて」
「リルダさん」
トモシが、笑う。
「みんな、リルダさんが頑張ってることくらい、分かってると思いますよ。だから、たまに力を抜いたって、誰も文句は言いませんって」
でも、と言いかけて、リルダはそれ以上口を開かなかった。そして、「今度何かあるときは、参加できるといいな」とこぼした。
「待ってますよ」
トモシは、リルダに大きく、手を振った。
ベルティルデ・バイエルは館の隅で、ナイト・ゲイルと話をしていた。
「ピクニック……ですか?」
「なにが起こるか分からないからな……念のための、警護も込み、だ」
「そうでしたか」
ベルティルデは、こくこく、と首を縦に振った。
「展望台に続く遊歩道を少し外れたところに、人目につかず、落ち着けそうな場所があった。それに、見晴らしのいいところも。簡単な地図を作って、渡しておこう」
「どうしてです?」
「あ?」
ベルティルデの質問に、ナイトの声が、低く返事をする。
「あんたが行ってもいいし、姫さんをさそってみるのもいいだろう。気分転換にはちょうどいい場所だった……。姫さんはよぉ、頑張っているのは間違いねぇ。だが、頑張り続けてるとよ、いつか緊張の糸が切れるぜ。長く続けるためには、適度な息抜きも必要だ。姫さん、その辺りの時間さえ取れてないだろ?」
「……なるほど、あなたのご心配は、もっともです」
ベルティルデはうなずくと、「ありがとうございます」と続けた。
「まあ…余計なお世話だろうけどな」
正面から感謝を言われたナイトは、少しだけ照れて、そう付け加えた。
「ま、もし行く気になったら、声をかけてくれよ。警護も必要だろう。都合をつけておく」
「ええ、そのときは、よろしくお願いしますね」
ベルティルデは、深く頭を下げた。
「そう……あれは死闘だった。みんなにとっては、のどかな日々の1ページに過ぎない……誰もが、にこやかに花を愛で、友人達と語らい合う……。だが、俺だけは戦っていたんだ」
ロスティン・マイカンは、おどろおどろしく、メイドたちの前で、そう切り出した。
「怪しい動きをしている奴を見て、俺はピンときたね。貴族を快く思っていない者、この閉鎖されたマテオ・テーペに悲観した者、かつては栄華を誇りながら、落ちぶれた者……。彼らにとって、ピクニックなんていう呑気な場所は、いい標的さ……」
恐ろしいほど熱のこもった話に、みな、息をすることも忘れたように静まり返って、彼の言葉に耳を傾ける。
「彼らがみんなに近づく前……道中の段差、茂みの中、展望台の陰……戦いは、密かに、けれど激しく、繰り広げられていたんだ……。俺は、奴らの背後に忍び寄り、得意の水魔法で――あ、いや……これについては、みんなには黙っておいてくれよ? 魔法は全くできない、ってことで通してるからさ――その水魔法で、相手の口をふさいで、気絶させて、問題が起こらないように、少しずつ手をかけていった……。中には俺に気付いて反撃する奴もいた。向こうの一撃を躱しながらこちらの一撃を叩き込む……それを相手が諦めるまで延々と続けて……」
彼は、熱弁によって、うっすらかいた額の汗をぬぐう。
「だからすまない、花を沢山持ち帰るつもりだったんだが、これだけしか……。……ということで、この埋め合わせはしっかりするから、皆のスケジュール教えてー!」
途端に調子の変わった彼の話に、メイド一同は、驚いてズッコケた。
領主の館を訪れる人がまばらになってきた頃、マティアス・ リングホルムはベルティルデ・バイエルと門の外で面会していた。
ベルティルデの手には、小さな白い花をたくさんつけた花が三本ほどあった。ふわりとした印象を与えるかわいらしい花だ。
この花は、ルース・ツィーグラーへのお土産だった。
「ありがとうございます。姫様もきっと喜びます」
「それならいいけど。姫さんの好み、わかんなかったから」
「姫様は、お花はどれもお好きですよ。このお花にも、ぴったりの花瓶を見つけるはずです」
厳しい面を見せることが多いルースも、花の前では甘い表情になるようだ。
何にしろ、喜んでくれそうでマティアスはひとまず安堵した。
「今日も、神殿に?」
「ええ。今日も滞りなくお勤めを果たせました」
「そっか、ご苦労さん。……そういえば、姫さんが仕事してる間、アンタは何してんだ? どこかで待ってるのか?」
「いえ、わたくしも微力ながら参加させていただいています」
へぇ、とマティアスは軽く目を丸くさせた。
「ほとんど毎日通ってるんだよな。疲れ、たまってないか? ちゃんと休めてるか?」
障壁維持の夜番昼番は交代制で、ルースもローテーションに含まれている。
休日はあるが、造船所へ行くことも多いルースがどれだけ休めているのか、マティアスは知らない。
彼の心配をよそに、ベルティルデはくすくす笑った。
「わたくし達は大丈夫ですよ。気にかけてくださってありがとうございます。姫様は体の芯が強いお方ですから、回復も早いですし」
「息抜きがちゃんとできてるなら、それでいいんだ」
「息抜きですか……そうですねぇ……」
何か気になることがあるのか、ベルティルデは考え込むような仕草をした。
「姫様にはもう少し、交友関係を広めていただければ……と思っています。さしでがましいこととわかってはいるのですが」
「俺は、姫さんの味方になりたいと思ってるよ」
「ありがとうございます。姫様はあの通り、ちょっと人見知りをするお方ですから、そう言っていただけると嬉しいです」
ルースのあの攻撃的な言い方を、ちょっとの人見知りですませようとするベルティルデも、なかなか大胆不敵である。
主従そろってどこかズレているのかもしれない。
「姫さんは、花の他に好きなものはあるのか?」
「音楽がお好きですよ。姫様ご自身もバイオリンをお弾きになりますし」
「花とバイオリンか。本当に姫なんだな」
改めて生活環境の違いを認識したマティアスを、ベルティルデは静かに見つめている。
「そろそろ帰るよ。姫さんによろしく伝えてくれ」
「ええ。次は、姫様も交えてお話ししたいですね」
ベルティルデに見送られ、マティアスは領主の館を後にした。
お久しぶりです、とリベル・オウスの前に現れたベルティルデ・バイエルは、前に会った時と変わらず元気そうだった。
「この前、俺の仕事のことを話したけど、実物を見せることはできなかったからな。展望台でちょうどいい花があったから、そいつを加工していくつか作ってみたんだ」
そう言って、リベルは持ってきた袋から小瓶を三つ取り出した。
一つ一つ中身が違うことに気づいたベルティルデは、何が入っているのか見極めようと小瓶に顔を近づけ、そのうちの一つを見て材料を言い当てた。
「これは、バラですか……?」
「よくわかったな。ちなみに、残りの二瓶も薬草の他にバラを使っている」
「え? そうなんですか?」
「まずは見事いい当てたこの瓶だけど、これは花びらを乾燥させたものだ。湯に混ぜて飲めば、安眠できたり昂った感情を静める作用がある」
「それはいいですね。今夜、さっそく試してみますね。どれくらい混ぜたらいいですか?」
「多くて五、六枚だ。あまり多いと味がきつくなる」
ベルティルデは興味津々に小瓶を見つめながら頷く。
リベルは説明を続けた。
「真ん中のは塗り薬だ。手荒れや多少の切り傷なら、これで治せる」
「ありがとうございます。助かります。開けてみてもいいですか?」
「ああ」
ベルティルデはリベルの手から真ん中の小瓶を手に取ると、慎重に蓋を開けた。
ふわりと、まろやかな香りが立つ。
「いい香りです」
と、口元を緩めるベルティルデ。
そして、三つめの小瓶は。
「こいつは、花の砂糖漬けだ。早めに消費することをお勧めする。ああ、味見はしてある。まずくはなかった」
妙な勧め方をするリベルの言葉に、ベルティルデがくすっと笑う。
それから三つの小瓶を大切そうに抱えて、リベルに礼を言った。
「こんなにいろいろいただいてしまって、何だか申し訳ないです。大事に使いますね」
「ま、使い方は任せる。自分に使うなり姫さんや他の奴に使うなり、好きにすればいい」
ぶっきら棒な言葉にも、ベルティルデの微笑みは変わらない。
「医師も多くいますけれど、薬師の方もまた心強いですね。そうやって誰かのお役に立てる技術があることは、とても立派だと思います」
「……追加はねぇぞ」
「お、お世辞じゃないですよ」
ベルティルデが余計なお世辞を言うような人ではないことは、リベルもわかっていた。
彼女があまりにまっすぐに言うものだから、少しだけ照れたのだ。
「たまには、外でのんびりするといい。特に、景色の良いところなら、いい気分転換になると思うぞ」
「そうですね。折を見て良い場所を探してみます」
「邪魔したな」
あまり長居しても迷惑になるだろう、とリベルは帰ることにした。
ベルティルデは、しばらくその背を見送った。
第5章 あなたと2人で
生まれつき病弱で体力のないマーガレット・ヘイルシャムには、山道は非常にきつく、バート・カスタルの助けがなければたどり着くことは出来なかっただろう。
「やっぱり殿方は力持ちですね」
用意した荷物は全て、バートが背負ってくれている。
展望台まで歩き、バートが下ろしたリュックを開けて、マーガレットは水筒を取り出す。
その時、バートはリュックの中を見てしまった。
入っていたのは、登山靴だとか、雨具にストック、ヘルメットやピッケル、寝袋……。
それはマーガレットが書籍で調べて借り集めた登山用具だ。
(何のために……いや、聞くのは失礼か)
とっても重たいこの荷物が、豪華なお弁当ではないかと期待していたなどと、一切口に出さず、ひとり耐える。
同時に、聡明な印象なのに、抜けてるところもあるんだななどと、密かに思っていた。
ベンチに並んで腰かけて、お茶を飲みながら風景を見る。
「カスタル卿が育ったのは、どのあたりですか? この地域の出来事なども、聞かせてほしいです」
「俺の生家は既に水の中だけど、遊び場は残ってるな」
バートは懐かしそうに昔のことをマーガレットに話していく。
町には漁師が多く、子供達も家業を手伝いながら、毎日忙しく、そして楽しく暮らしてきたとのことだ。
「神殿や領主の別荘は、公国が独立する前からあったんだ。山小屋なんかは、港町の住民が作ったらしい」
いつしか彼は立っており、あの辺りに、この辺りにと、目を輝かせて場所の説明や、過去の出来事を語っていた。
「……って、ゴメン。君の活動には関係のない話だったな」
「いいえ、どのようなお話も、興味深いです」
マテオ・テーペ回顧録の執筆を予定しているため、ここから一望できる風景について説明してほしいとお願いし、バートに同行を頼んでいた。
だけれど、マーガレットには他にも執筆しているものがあるから。
この土地以外の情報も得て損はないのだ。
「では、そろそろ帰りま……」
立ち上がりかけたマーガレットは、ふらりと倒れかかってしまう。
「っと、大丈夫か?」
瞬時にバートがマーガレットの肩を支えた。
「大丈夫です、少し眩暈がしただけですので」
「そういえば、顔色あまりよくないな。平地だったら、抱き抱えていくところだけれど、山道だからな……転んだら、君をつぶしかねない」
バートの体重+マーガレットが用意した登山用具の重さはマーガレットの体重の3,4倍ありそうだ。
「歩けます」
ただ、登りと同じように、時々手だけ貸してくださいと言い、マーガレットは帰路についた。
バートに助けてもらいながら、時間をかけてゆっくりと山を下りて、馬車が待つ場所までたどり着く。
「今日は貴重な経験が色々と出来ました。ありがとうございます。ご迷惑も沢山おかけしてしまい、申し訳ありません」
マーガレットがそう言うとバートは普段通りの爽やかな笑みを見せる。
「こちらこそ、楽しませてもらった。ただ、次は出発前に荷物の中身は確認させてもらおうかな……ワクワク感は薄れるけど」
「はい?」
「ははっ、ゆっくり休んで、疲れとれよ」
「ええ、今日はしっかり休みます」
(言えませんね、ええ、言えませんよ。昨夜は薔薇騎士物語の筆が走って、気づいたらもう明け方で、実はほとんど寝ていなかったなんて……)
彼女がふらついた理由はただそれだけだった。
水の障壁を背にして、町が見える場所にアリス・ディーダムは、レイザ・インダーと並んで腰かけた。
がさこそと鞄の中から取り出して、どうぞと差し出したのはお弁当だ。
「この間、泳ぎを教えていただいたお礼も兼ねて、作ってきました」
「手作りか。アリスは自分で料理が出来るんだな、大したものだ」
レイザはフォークを手に取って、まずはポテトサラダを自分の口へ運んだ。
「あ、飲み物入れますね」
アリスは緊張しながらそわそわと水筒を取り出して、コップにお茶を注いだ。
「うん、良い味だ。料理上手いんだな」
続いて、唐揚げを食べながらレイザが言うと、アリスはほっと安堵の笑みを浮かべる。
「得意というほどではないんですが……嬉しいです」
自分でもお弁当を食べて、のんびり景色に目を向ける。
ここには、10年ほど前に両親と来たことがある。
その時、お弁当を作ったのは勿論自分ではなくて……。
「私が魔法学校に入ったのは、魔法を習得して魔術師になって両親と一緒に世界を回る為です。
危険なことも多いからと両親は反対してましたけど。あ、私の両親、2人とも優れた魔術師で、世界を飛び回っていたんです」
「アリスは才能もあるし、ひたむきに頑張っているから、親御さんにとって自慢の娘になるだろう。だが、心配はかけ続けてしまうかもしれないな、色々な意味で」
何故かアリスの胸元を見ながら、くすっと笑うレイザにアリスは頷いて。
「レイザ先生は魔術師になりたかったんですか? 小さい頃の夢を聞いても良いですか?」
真っ直ぐな目で、彼に尋ねた。
「夢か……」
アリスの問いに、レイザはしばらく考え込んだ。
「魔術は嫌いじゃなかったし、なりたかったかと言えば、なりたかったとは思う。夢はあったような、なかったような……。曖昧な答えですまない」
レイザが謝罪すると、アリスは首を左右に振った。
それから、お弁当を食べながら一緒に、景色を眺める。
もう、見ることが出来なくなってしまうかもしれない、ここに広がる景色を。
「両親はここには居ませんがどこかで生きてると思います。旅行好きで1年帰って来ないのは普通でしたから」
アリスは涙をこらえて、悟られないよう笑顔を浮かべる。
レイザは何も言わずに、彼女の頭に手を回して、励ますようにぽんぽんと優しくたたいた。
気休めになるような言葉を、彼は何も言わない。
だけれど、彼の手から感じる優しい温もりが、アリスの心を落ち着かせていった。
「あの、ここのお花ですが、根ごと持ち帰ってもいいでしょうか? 寮の花壇に植え替えたいんです。こんなに綺麗なのに、もう見れない可能性があるなんて寂しいですから」
「そうだな。俺も手伝おう」
そして、食事を終えてから、2人は植え替えるために花をいくつか抜いた。
「少し、時間くださいね」
その他に、アリスは花を摘んで冠を編んでいった。
「小さい頃に作ったけど、まだ覚えてるものですね」
ペチュニアの花を編み込んだその冠を、レイザの頭に乗せる。
「似合ってますよ」
「……ありがとう」
レイザは少し照れくさそうな笑みを見せた。
その姿はこの場の景色と共に、新たな思い出としてアリスの胸に刻まれた。
山の中の花が野生している場所に、ウィリアムはアーリー・オサードを誘って向っていた。
港町の民である彼が、過去に仲間と共によく訪れていた場所だ。
「チビ達がぐずったり、機嫌悪くなってどうしようもなくなった時に、ここに来て詫びのつもりでここの花で冠を作って渡してたんだが、びっくりするぐらい機嫌が良くなってな……」
「……そんな場所に私を誘うって、どういう意味かしら?」
憮然と自分を見るアーリーに、ウィリアムは苦笑する。
「いや、子ども扱いしてる訳じゃなくてな」
何故だろう。
自分でもよくは分からなかった。
少しでも、笑顔になってほしいのかもしれない。
「本来は仲間内で使ってて、花屋や、薬屋、仲の悪い夫婦の旦那さんに仲直り様に売ったりして小遣いを稼いでた訳だ。確か最後に行ったのは洪水前だな」
山道を歩き、少し開けた場所に出た。
だけれど、そこには以前のような花畑ではなくなっていた。
「参った、この場所も変わってしまうなんてなぁ……」
「形跡もないけど」
「いや、本当に花畑あったんだって。ちょっと探してみるか……」
ウィリアムは意地になって、付近を調べ始めた。
諦めたら、思い出までも消えてしまいそうな気がして。
「あった」
弱い花々は無くなってしまっていたけれど、生命力の強い花がほんの少し、残っていた。
ほっと、息をついて、ウィリアムはアーリーを呼んだ。
「ほらみろ、逞しく生きてるだろ」
「……周りの花が死んだことで、その分光を浴びることができ、養分も得られて、生き延びたのよ」
「言い方も、見方も変えれば嬉しい気持ちにならないか? それにさ、仲間たちが居たことが、否定されなかった気がして、嬉しいんだ。……って、完全に俺の気分転換だな」
言って、ウィリアムは他の花を傷つけないよう、白く美しい花を一輪とって、アーリーに差し出した。
「詫びだ」
「……綺麗ね」
花を受け取り、そして健気に咲く花々をアーリーは見る。
「自然に罪はないのに、人は自然と共に生きることを望まず、支配しようとして、そして滅ぼす。ここももうすぐ沈むわ。思い出と共に」
「そうか」
答えた後、ウィリアムは景色を眺めていた。
脳裏に浮かぶのは、以前の花畑。そして大切な仲間たちの姿。
「あのさ、あなたの声、全然絶望を感じないんだけど。私の話聴いてる?」
「ん? もちろん聞いている」
「変な人よね。特にその髪型。根暗で陰湿な友達なんかいない男かと思ったら、全く違うし」
「そんな風に見えていたのか」
「ええ。……私はどう見えていた? 根暗で友達いなそうだったでしょ?」
そうは見えなかったが、確かに明るい印象ではなかった。
「今ね、私結構楽なのよ。目立たないように、当たり障りないことしか言えなかった頃より、こうして言いたいことはっきり言えて。
人間、嫌いだし、あなたに嫌われても構わないし、なんなら今、殺してくれても構わない」
挑戦的な目で微笑しながら、アーリーはウィリアムを見る。
「前髪切ってあげようか。ハサミならうちの雑貨屋にあるし……。まあ、もう何もかも沈んでしまったでしょうけど」
目を伏せて、彼女はすっと背を向けた。
「戻りましょう」
アーリーを追って歩きながら、ウィリアムはそっと後ろを振り返った。
花園の中、記憶の中のチビ達は帰りたくないと、駄々をこねていた――。
「来てくれてありがとう、サーナ」
ラトヴィッジ・オールウィンは、サーナ・シフレアンを見晴らしの良い場所へと、誘い出していた。
「足元、気を付けて。お手をどうぞ」
ラトヴィッジが手を差し出すと、サーナは細く小さな手を彼の手に重ねてきた。
彼女の手を取って、ラトヴィッジは野生の花畑が見える場所へと導いた。
足元にも、ぱらぱらと白い花が咲いている。
「サーナは花は好きか?」
「うん。ラトヴィッジは?」
「俺も好きだ」
ラトヴィッジは身をかがめて「一輪貰うな」と言いうと、シロツメクサを一輪抜いた。
サーナの指をとって、くるくる輪を作って指輪を作り出すと、彼女の中指に嵌めた。
「器用だろ」
笑いかけると、サーナはこくりと頷く。
「誰に教えてもらったの?」
「昔、孤児院に居た頃に姉さん達に」
「孤児院?」
頷いて、昔を懐かしみながらラトヴィッジは話す。
「物心ついた時には孤児院に居て……でも全然寂しくなんて無かったんだぜ? 孤児院には優しい姉さん達が居た。同じ孤児同士、姉さん達はとても優しかった。
春は外で、野の花でこうやって指輪を作ったり花輪を作ったりして」
「それで……どうして騎士に?」
家柄か、もしくは優れた能力がなければ、騎士になるのは難しく。孤児院では才能があっても能力を伸ばすことは困難と思えた。
「孤児院には時々、孤児を引き取りたいって人が来た。皆、その時は自分が呼ばれる事を期待してた。何時までも孤児院には居られない事は理解っていたから」
そして、ラトヴィッジはある日、突然選ばれたのだ。
騎士の家系の養父母に。
「俺が選ばれた理由は単純。男で、髪と目の色が養父に似てたから。それだけで選ばれた俺を、姉さん達は祝ってくれて笑顔で送り出してくれた。イイ男になれって」
その時からずっとラトヴィッジは考えていた。
自分は何者なんだろうと。
「養父母はよくしてくれたけど……『俺』だから選んだ訳じゃない。俺は俺を選んでくれる人を、ずっと待っていたのかもしれない」
自分の話を静かに真剣に聞いているサーナの頭を、ぽんぽんとラトヴィッジは2度優しくたたいた。
「だからさ、サーナに頼られて俺は嬉しかったって話。それを伝えておきたくて」
彼女を見詰めて、目を細めて微笑みかける。
「有難う、サーナ。俺を見つけてくれて」
「ラトヴィッジ……」
薄らと涙を浮かべ、
「ありがとうって言ってくれて、ありがとう」
「サーナの事も教えてくれないか? 幼い頃、どんな子だった?」
「……どんな子だったのかな、私」
サーナは花畑を見ながら、昔の事を思い浮かべる。
「ただ、皆、大好きで……。お仕事してる神殿の人や、騎士さんたちに、まとわりついて……色んな話聞かせてもらって、遊んでもらったり、肩車してもらったり……。男の人が多かったから、こんなふうに、お花の指輪つくったりしたこと、なかったな」
「明るい子だったんだね?」
「たぶん……」
少し、沈黙した後、サーナはラトヴィッジを見上げた。
「今はいいの、ラトヴィッジだけで。私の騎士になってくれて、ありがとう」
サーナは身を寄せるとラトヴィッジの腕にぎゅっと抱き着いて、目を閉じた。
「温かい……。もう少しだけ。長くは望まないから……こうして、いたい」
「傍に居る。ずっと」
優しく、それでいて力強い声で、ラトヴィッジが言うと、サーナは彼の腕に頬を寄せて頷いた。
■執筆担当
1~4章の☆ ☆ ☆までが東谷
☆ ☆ ☆から* * *までが冷泉
* * *以降は川岸
5章は全て川岸
オープニングストーリー、鈴鹿
■ライターより
こんにちは、ライターの東谷です。
美味しいお弁当でピクニック、いいですよね。
昔、キャベツの千切りと白米だけのお弁当を作ったら、「親に弁当って作ってもらったことないの?」と同情されたことがありますが、単純に料理スキルとかの問題で、それ以上のものが作れなかっただけです。
今回のイベントシナリオでは、そんなひもじい弁当ではなく、ちゃんとしたもので、ピクニックを楽しめているようだったので、非常に安心しました。
こんにちは、執筆を一部担当しました冷泉です。
我が家の近くにも展望台はありまして、そこから見える海はお気に入りです。
四つ葉のクローバー探しも、もちろんやりました。
今でも道端などにクローバーがあると目が……。
それでは、今回もご参加いただきありがとうございました!
一部担当させていただきました、川岸です。
先日突然誘われて、ハイキングに行ってきました。5時間位山の中を歩いたみたいです。
展望台までの道は、こんな感じなのだろうなとか、あのシーンではこんな景色が見られたのだろうとか、イメージが膨らみより楽しめました。
少々切なげなシーンもありますが、マテオの皆にとってもとても楽しい一日だったと思います。ご参加、NPCのお誘い、ありがとうございました!
